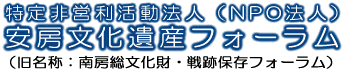◎講演抄録(房日新聞2010.6.16付)
.
心の過疎をつくらないまちづくり
-新たな公とは何か-
--住民参画の仕組みを導入--
矢野学氏(新潟県上越市議・旧安塚町長)
.
雪国の安塚の取り組みを紹介する。合併して21万人の上越市になったが、安塚地区は3300人の中山間地。私は平成17年の合併時の町長だった。合併で「必ず行政サービスは落ちる」と思った。自分たちが元気を出して自前の地域、特色と活力ある地域をつくろうと腐心した。
そのために自分たちでお金も責任も行動もしようと。その仕組みとして「NPO法人・雪のふるさと安塚」という自治組織をつくった。これが「新しい公共」として全国で紹介されることになった。
雪を使った町おこし。また景観をきちっと考えようと、公共施設は木造にしている。ごみの集積所も。行政だけでなく、市民の力もある。花いっぱい運動にも取り組んだ。オリジナルの花をと、ヤナギバヒマワリが全町で100万本咲き誇る。今200万本を目指している。
財団をつくって、雪を利用する研究をした。雪室をつくり夏の冷房に使っている。コメの貯蔵、農産物の保存にも使う。福祉の施設や中学校も雪冷房している。雪1㌧で二酸化炭素30㌔を削減し、石油10㍑を節約できる。雪は邪魔者ではなく、資源になった。現在、世界一の雪の保存量があるのが安塚という地域だ。
棚田の町を売り出そうと、子どもの田舎体験事業に取り組んだ。特徴は民泊ができること。世帯数の2・5割が経験している。今は1億円の産業になった。
新たな自治組織(NPO)には1人年2000円の会費で、世帯数の8割にあたる1167人が加入した。分科会に分かれ、地域をどうするかを考える。最初の理事長は女性。上越市から4000万円の委託を受け、施設の管理も行う。独居老人の見守り、有償ボランティアも引き受ける。
上越市は「協同のまちづくり」の目的で各地域に自治区を制定。地域の意見を取りまとめる「地域協議会」も設けた。各区10-20人の委員は選挙で選び、無報酬。地域をどうするかを考え、市から委託を受けたものを審議する。年2億円の活動資金が市から自治区に配分される。安塚地区には約600万円。何に使うかは協議会で話し合って決める。
館山は合併はなかったが、合併しようとしまいと、新しい公共になるにはどうするか。市民の皆さんの意見をどういう風に行政が聞いて、トップの市長が皆さんに回答し、あるいは意見を求める。そういう仕組みをどうつくるかというのが、自治体の元気のあるかないかで差がつく。
今どちらかというと、館山市はたたずんでいるのではないかと思う。それは、仕組みをつくっていないから。行政に元気がないのか、市民の皆さんにアイデアがないからたたずんでいるのか。
私のように3000の人口でしかないところが、いま交流人口がゼロから50万人になった。雪を売って、町を花でいっぱいにし、棚田でいろいろな子供たちが来て体験をし、ある時には涙を流して帰る。
私どもは、まだ未知のものだが、目指すべき公共、市民のみなさんと情報を共有し、市民の参画を得よう、皆さんからもらった税金を自由に使うために考えていこう、このようなことをたたずまないで前に進もうと、新しい仕組みをつくって実践中だ。
その中で安塚は特にコミュニティがしっかりしているから、経済活動もコミュニティビジネスも生まれてきて、自分たちが自信を持つ自治体像を語れるのではないかと思う。一人一人が考え、実行することが大切だ。
◇ ◇ ◇
本稿は、12日に館山市の南総文化ホールで開かれた「まちづくりシンポジウム」のスピーチを要約したものです。
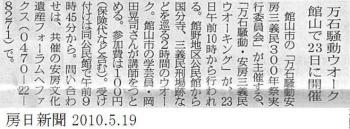
万石騒動ウォーク、館山で23日に開催
.
館山市の「万石騒動安房三義民300年祭実行委員会」が主催する、「万石騒動・安房三義民ウォーキング」が、23日午前10時から行なわれる。館野地区公民館から国分寺、三義民刑場跡などを巡る2時間のウォーク。館山市の学芸員・岡田晃司さんが講師をつとめる。参加費は100円(保険代などを含む)。受け付けは同公民館で午前9時45分から。問い合わせは、共催の安房文化遺産フォーラムへファックス(0470-22-8271)へ。
(房日新聞2010.5.19)
⇒⇒開催概要はコチラ。

■美術界の有志ら、NPO設立
故・平山郁夫氏 発起人に名連ね
.
明治期の洋画家・青木繁が若き日に滞在し、代表作「海の幸」を制作した館山市布良の小谷家住宅=昨年11月に市有形文化財に指定=の復元・保存を支援しようと、日本美術界の有志らが「青木繁『海の幸』会」を設立。特定非営利活動法人(NPO法人)としてこのほど、法人登記申請が受理された。
[ .. 全文表示へ ]

女性初の館山市名誉市民で(財)館山ユネスコ保育園園長の本多馨氏が7日午後7時42分、胆管がんのため亀田総合病院で死去した。87歳。自宅は館山市館山582.前夜式が9日午後6時から、葬儀は10日午後1時から、いずれも館山市北条の館山斎場で営まれる。喪主は長男慶晴氏。
同市文化団体連絡協議会(現・芸術文化協会)や南総文化ホール友の会会長などを歴任し、長年にわたって地域文化の発展に貢献。県保母会長として、保母の資質向上や身分保障に関する研究調査などにも活躍した。
また、館山音楽鑑賞協会の会長として、広く市民参加を呼びかけてステージ演奏の機会を企画し、市民とともに鑑賞する活動を展開。草の根ボランティア活動から設立された館山国際交流協会では、文化交流第一委員会委員長として、自主的活動による文化分野での国際交流を促進。誠実で温厚な人柄と包容力は、周囲から絶大な信頼を得ていた。
こうした功績が評価され、昨秋の市施行70周年記念式典にあたり、女性として第一号となる名誉市民の称号が贈られた。

映画『日輪の遺産』、終戦の悲話、来年公開
館山・南条の里山でロケ
堺雅人・中村獅童らが迫真の演技
.
来年の公開を目指して制作中の映画『日輪の遺産』(浅田次郎原作、佐々部清監督、角川映画配給)のロケが13日から16日までの4日間、館山市南条の里山周辺で行なわれ、主演の堺雅人や中村獅童、ユースケ・サンタマリアなど銀幕のスターが迫真の演技を繰り広げた。
同作品は昭和20年夏、終戦間近の東京周辺が舞台。帝国陸軍の真柴少佐(堺)が軍トップに呼び出され、山下奉文将軍が奪取した巨額のマッカーサー財宝を秘密裏に隠匿せよとの指令を受けるという、スリルと悲劇のストーリー。真柴は部下とともに、勤労動員少女を使って任務を遂行していく。
館山のロケ地は今回、財宝の隠し場所という設定で、撮影舞台が乗り込んだ。
記者が取材を許されたのは14日午後。山中にはこうこうと撮影用のライトが照らされ、当時の陸軍トラックが運び込まれるなど、大がかりなセットが組まれていた。
当日は晴天に恵まれたものの、前夜の雨で足もとが若干ぬかるんでいる。物語は真夏の設定であるため「朝からバーナーを使い、地面をくまなく乾かして撮影可能にした」(角川映画広報担当者)という。
現場では、砲弾が入っているようにカモフラージュした財宝入りの木箱を、中村獅童演ずる望月曹長がトラックの荷台から下ろすシーンを撮影中。女学生役の20人が作業を手伝い、木箱を防空壕に運ぶ。
『半落ち』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した佐々部監督は、穏やかな表情でシーンごとの動きを出演者らに説明。入念にリハーサル、カメラテストを繰り返していく。いよいよ収録。スタッフの「本番でーす!」の声が響くと、周囲の雰囲気が一瞬にして張りつめた。
今回のロケ実現にあたっては、館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラムが尽力。現場で撮影に立ち合っていた角川映画の北尾知道専務は「地元の方々の協力に感謝している。クランクインして2か月近くになるが、いい絵が撮れている」と話していた。
◇◇
ロケ現場での報道用撮影は許可されず、併用写真はいずれも角川映画提供のものです。
(房日新聞2010.5.21付)

南房漁村の雰囲気満喫たてやまエコウォーク盛況
青木繁没後100年を記念
.
南房の自然や文化、人情に触れながら散策する「たてやまエコウォーク」が館山市の平砂浦、布良、相浜地区で催された。県内のみならず、都内や横浜市などから34人が参加し、漁村の雰囲気を満喫した。
今回のエコウォークは、「海の幸」などで有名な明治期の洋画家、青木繁が滞在し「海の幸」を描いた市文化財にもなっている同市布良の小谷家住宅を巡った。ガイドを務めたNPO安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄理事長)は「青木繁没後100年事業のキックオフにしたい」と話す。今回の参加費の一部は小谷家の修繕・保存費として寄付された。
昼食に立ち寄った相浜では相浜漁協(天野光男組合長)が浜揚げ解禁直後の伊勢エビを用意し、サザエなどと海鮮バーベキュー。参加者らは「味付けなしでおいしい」と舌鼓を打った。例祭に当たっていた相浜神社では、伝統のおはやしに拍手を送った。
エコウォークは、地域のガイドと一緒に歩き、通常の旅行では見落としてしまいがちな文化や特徴を発見する「歩いて楽しむエコツーリズム」運動の一環で、日本エコウォーク環境貢献推進機構が進めている。館山市では市内のNPOや各種施設などが「たてやまエコツーリズム協議会」を結成して8コースを設定、普及に努めている。
(千葉日報2010.4.1)
(房日新聞2010.4.8付)
教育旅行 21年度は50校受け入れ 館山
豊富なメニューで年々増加
.
地域資源を活用した体験観光を目玉に、教育旅行の誘致に力を入れる館山市の21年度実績がまとまった。受け入れた学校数は、昨年より4校増えて50校を数え、無人島探検やビーチコーミング、田植え体験など豊富なメニューに、延べ6007人(前年比1757人増)の子どもたちが「館山」を体感した。
[ .. 全文表示へ ]
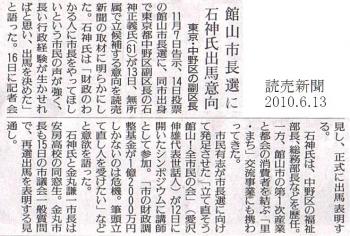
(読売2010.6.14)
11月7日告示、14日投票の館山市長選に、同市出身で東京都中野区副区長の石神正義氏(61)が13日、無所属で立候補する意向を読売新聞の取材に明らかにした。石神氏は「財政のわかる人に市長をやってほしいという市民の声が強く、長い行政経験が生かせればと思い、出馬を決めた」と語った。16日に記者会見し、正式に出馬表明する。
[ .. 全文表示へ ]

(房日新聞2010.6.8付)
文化遺産フォーラムが部門賞
まちづくり教育に高い評価
.
地域の歴史・文化財の保存・活用を通じたまちづくりに取り組んでいる館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラムの活動が、第8回日本都市計画家協会賞の「まちづくり教育部門賞」を受賞することになった。
19日に東京で行なわれる同協会総会で、表彰式が行なわれるという。
同フォーラムは昨年、文化財保存全国協議会の「和島誠一賞」を受賞しており、これで全国的な組織から2年連続で高い評価を受けることになった。愛沢伸雄代表は「われわれの活動だけではなく、地域の市民の力が認められたと思っている。受賞は活動メンバーの励みにもなり、とてもうれしい」と話している。
日本都市計画家協会は、都市・地域計画の専門家などで組織。調査・研究や政策提言、社会啓発など都市・地域分野にかかわる分野で幅広い事業を展開している。
同賞は、全国のまちづくりの取り組みの中から「優れた理念を持つ活動や計画、策定プロセス、手法」などを表彰。「まちづくり教育部門」は大賞に次ぐ高位の賞と位置づけられている。
安房文化遺産フォーラムは今回、▽赤山地下壕など地域の戦争遺跡の保存とガイド事業の実践、ガイドブックなどの作成▽稲村城跡の保存と、里見氏ゆかりの他地域との交流▽青木繁の名画「海の幸」誕生の家と記念碑の保存・活用への取り組み▽地元の食文化、生活文化の記録伝承…など、これまでの総合的な取り組みが「平和・交流・共生の地域づくり」として評価された。

青木繁ゆかりの地歩く〜27日にエコウォーク
.
「海の幸」を描いた画家の青木繁が亡くなってから、来年で100年の節目を迎えるにあたり、たてやまエコツーリズム協議会(三瓶雅延会長)が27日、館山市富崎地区のゆかりの場所を歩くエコウォークを開催する。
青木繁が滞在した小谷家住宅(市指定文化財)や、没後50年に建立された海の幸記念碑などを地元のガイドとともにめぐり、画家の愛した風景と漁村文化を体感してもらう。
同地区は、かつてはマグロ延縄漁で活気づいた小さな漁村。明治時代には、青木繁がここに滞在し、代表作となる「海の幸」が誕生した。現在も、当時の暮らしの面影を色濃く残す漁村風景が多く残っている。
今回のエコウォークは、地域の歴史的環境保全に努めている同協議会のNPO法人安房文化遺産フォーラムが中心となって担当。眼前に広がる大海原を眺めながら、同フォーラムのガイドで地元の人たちとも交流する。昼食には、地元漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を使った浜焼きが提供される。
ウォーキングは午前10時30分〜午後3時ごろまで予定。安房自然村=海の幸記念碑=小谷家住宅=布良崎神社=安房節記念碑のコースを歩く。参加費は5000円。
申し込み、問い合わせは、南総JAM事務局の井坂さん(080-6530-4553)か、いこいの村たてやまの工藤さん(0470-28-2211)まで。