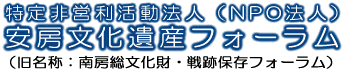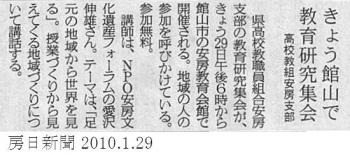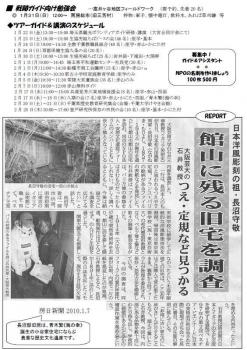高齢者、乳児の医療費を無料化した村長描いた
映画「いのちの山河」上映へ
.
.
館山市を中心とした市民グループ「安房の地域医療を考える会」(愛沢伸雄代表)は、全国で初めて老人・乳児の医療費無料化を決断した岩手県(旧)沢内村の深澤晟雄村長の半生を描いた映画「いのちの山河・日本の青空Ⅱ」の上映会を、3月6日に南総文化ホール大ホールで行うことを決めた。
[ .. 全文表示へ ]
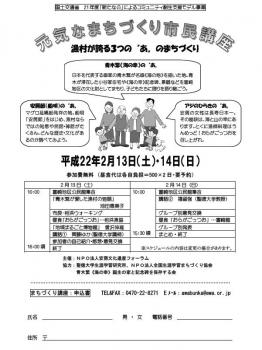
元気なまちづくり市民講座
=3つの〝あ〟のまちづくり=
(国土交通省・平成21年度
「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業)
.
■日時:平成22(2010)年2月13日(土)14日(日)10:00〜16:00
■会場:館山市富崎地区公民館
■参加費:無料(昼食代は各自負担500円:要予約)
.
【13日(土)】
・「青木繁が愛した漁村の物語」池田恵美子
・布良・相浜ウォーキング
・昼食「おらがごっつお」…相浜漁協(要予約500円)
・「地域まるごと博物館」愛沢伸雄
・講話①齊藤ゆか(聖徳大学講師)
・参加者の自己紹介・感想・意見交換
.
【14日(日)】
・講話②福留強(聖徳大学教授)
・グループ別意見交換
・昼食「おらがごっつお」…富崎館(要予約500円)
・グループ別発表
.

.
館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラムは13、14の両日、同市の富崎地区公民館で「元気なまちづくり市民講座」を開催する。
14日午前には、生涯学習まちづくりブームの「仕掛け人」として知られる福留強・聖徳大学教授が「日本各地のまちづくり活動の実践事例」について講演。13日には愛沢伸雄・同フォーラム代表の講話や、布良・相浜両地区のウォーキング・イベントなどが予定されている。
また、地域が抱える課題の解決方法を探る「グループ別意見交換」も連日行われる。
両日とも午前10時から午後4時ごろまでの予定で、参加費は無料。同フォーラムの池田恵美子事務局長は「富崎地区に限らず、まちづくりに関心のある方〃はぜひ参加してほしい」と話している。
問い合わせ、申し込みは同フォーラムへ。電話、ファクス0470-22-8271。電子メールはawabunka@awa.or.jp
.
(房日新聞2010.2.7付)

【講演抄録】「考古資料からみた安房神社成立の基層」覚書
古くから人の住んだ場所、海人集団首長の崇拝地か
安房歴史文化研究会会長 天野努
(房日2010.1.28)
安房神社の成立のもとはどういうことだったのかを考古資料から考えていく。
文献資料では忌部広成が書いたといわれる「古語拾遺」と、天皇の食膳を担当していた高橋氏による「高橋氏文」の2つの氏族伝承がある。今までは「古語拾遺」が多く語られていたが、最近の文献史学では新しい史料が発掘され、「高橋氏文」は史実を反映しているものだとされるようになった。
「高橋氏文」では▽安房のカツオと貝がセットで天皇の食膳に提供されていること▽高橋氏の祖先が天皇から「大伴部(おおともべ)」と呼ばれる部民を賜ったこと▽安房大神(あわのおおかみ)を御食都神(みつけかみ)として大膳職の祭神としていたこと—などが書かれている。
これまでの記述を証明するものはなかったが、731年の「類聚三代格」という文書の中に、「安房地方で安房大神を祀っていた女性たちが上京して宮中の御食都神を祀ることを命令されていた」ことを示す内容が見つかった。当時は安房神社は、安房大神と言われていたようだ。
これを考古学の資料からみるとどうなるか。
安房の漁村型集落遺跡の沢辺遺跡(南房総市白浜町)では、7世紀ごろの疑餌針が出ている。カツオの骨とウロコもたくさん出てきた。カツオ漁が行われていたのは確かで、「高橋氏文」の内容と符合している。
出土した貝はサザエが多いのだが、アワビオコシの道具も出ている。
平城京跡などから出土した木簡には、安房の「大伴部」がアワビを献上したことが記されている。出土木簡に書かれている「大伴部」姓は安房の人以外にはなく、このことからも「高橋氏文」の内容は史実だと考えられる。
一昨年、昨年と千葉大学の考古学研究室が、安房神社の境内にある安房神社洞窟を再調査した。洞窟のある場所は、6000年前の縄文海進で海が一番高くなった「沼1面」にあたる。出てきた一番古い土器は縄文前期。縄文海進が終わって陸化し、その段階で洞窟になっていたところに人が住み始めている。
安房神社の境内でも以前、縄文時代の土器が採取されたという。安房神社のある所に古くから人が住んでいた場所だ。
境内から出土して、安房神社が今も所蔵している高坏、5世紀のもので市の文化財に指定されているが、これが館山市沼の大寺山洞穴遺跡から出たものとまったく同じ特徴を持つ。安房神社のものは祭祀に使われたと考えられている。
大寺山の高坏は舟形木簡の副葬品だった。時代は同じ。形がまったく同じ高坏は、この2ヶ所以外では出ていない。大寺山では他に鉄の兜、短い鎧が出ている。これも5世紀のもの。短い鎧は房総では珍しいが、ふつうは古墳から出てくる。それが海岸近くの洞窟から出てきた。この遺跡に葬られた人々は、安房の海人集団の首長だと考えられる。
房総半島の中で、祭祀遺跡は(古代の)安房郡=注:現在の館山市、旧白浜町を主とする地域=に集中する。白浜の小滝涼源寺遺跡は4世紀後半からの遺跡だが、石製模造品と言われている剣や鏡が伴っている。祭祀が早い段階で行われていた。房総にはヤマトタケルの伝承もあるが、大和朝廷の東北支配にかかわる遺跡ではないかと考えられている。
5世紀の遺跡になると、土器を使った祭祀品が出てくる。
安房の地域には古代からの漁労民の集落があり、祭祀遺跡や洞穴遺跡がある。特に大寺山遺跡と安房神社境内に同様の出土品がある。安房神社のある場所というのは海人の首長に崇拝される、地域の人にあがめられる、そういう場所だったのではないか。
神社が形を持ってくるのは、天武天皇の時代の7世紀後半から。安房は5世紀ぐらいに大和朝廷の支配下に入っていく。当時の漁労種族、房総半島を回るときの水先案内人のような人々がいて、その中心的崇拝地が安房大神、それが安房神社になったのではと考えられる。
(本稿は平成22年1月23日に館山市コミュニティセンターで行われた同研究会公開講座の内容を要約・再構成したものです)
【講師】新屋敷孝氏
【テーマ】夢は実現させるもの
本州最南端の佐多岬から日本最北端の宗谷岬まで3,400kmを3ヶ月で走りぬいた新屋敷さんのマラソン人生とこれからの夢を語っていただきました。
[ .. 全文表示へ ]


館山の空を飛んだ落下傘兵から山頭火を描く画家へ…
秋山巌さん(松戸市在住)
聞き手=池田恵美子
死の恐怖と生の喜び
館山の訓練で教わる
昭和16年、海軍で落下傘部隊に選抜されて館山で訓練を受けた。高度300mで航空機から飛び出し、パラシュートを広げて館空に着地する。飛び出した瞬間は目の前が真っ暗になる。尻込みしても、容赦なく空中にたたき落とされる。
落下傘が開かないで、地上に激突し死んだ者もいた。風が強いと空中で流され海に落ちる。すぐ救助隊が出るが、これも間に合わないで死んでいく。次は自分の番かもしれない。だが訓練を拒否することはできない。一度飛ぶと10円もらえた。今の10万円ぐらいの価値があった。だが金を残す気はなかったですね。
台湾の基地を経由して、開戦後の17年初めにティモール島のクパン(現インドネシア)に上陸。最初の2日間の戦闘で、部隊500人のうち30数名が負傷した。その後はミレ島(マーシャル諸島)の警備などをして、同年暮れにいったん日本に戻った。自転車より遅いのではという貨物船に乗った。米軍の潜水艦攻撃が怖くて、夜は板きれと水筒を持って甲板で寝た。
18年に館山砲術学校で各種兵器の取り扱い訓練を受け、部隊を再編成。サイパンへ向かう前に、アッツ島へ応援だと言われた。2万人の米兵の中に突っ込めという作戦だった。これは中止になったが、アッツ島の日本兵は見殺しになった。
サイパンでは、ガダルカナルに向かい敵を襲撃する200名の部隊に選抜された。「たった200人で何ができる」と疑問に思ったが、反抗できるわけもない。泣く泣くサイパンを発ったが、数ヶ月後にはサイパンに米軍が上陸した。私は結局ラバウルにいて他の部隊の応援などをし、そこで終戦を迎えた。運がよかったとしかいいようがない。
終戦時は対空砲の担当。それまで毎日グラマン(戦闘機)などが来襲していたのに、8月14日は来なかった。おかしいなと思っていたら、15日に敵機が低空飛行して「日本は降伏した」とビラをまいた。暗号兵の友人からそれらしき話も聞いていたし驚きはなかった。ホッとして、やれやれという気持ちだった。
私は大分県竹田生まれの百姓の子。近くの寺の和尚が墨絵を描いていて、8歳のころから手ほどきを受けていた。
戦後、坂本繁二郎さんがやっていた太平洋美術学校に入り、毎日デッサンをしていた。坂本さんは寡黙な先生で「この線はいかん」とか注意はするが叱りはしない。ほどなく先生は郷里の福岡に帰られてしまい、新しく来た先生が気に入らなくて学校は辞めた。
棟方志功との出会いは、日本橋に絵の具を買いに行き、白木屋(デパート)で展覧会を見たこと。躍動感と墨の色にひかれ、次の日も見に行った。それで門下生となり、版画の世界に入った。
彼の有名な言葉だが、棟方さんには「お前の絵には化け物がない。化け物を出せ」と何度も言われた。後日、大原美術館でその言葉の由来を聞いた。昭和初期、柳宗悦が初めて棟方の版画を見た時、京都の河井寛次郎に「化け物を見た。すぐ来い」と電報を打ったのだという。
柳宗悦さんが棟方に「井戸は2本掘らなければダメだ」と話したという。絵一本でなく、想像力をつけるために文学や詩を読めと。私は遠野物語を絵にしようと東北に通ったり、一茶や西東三鬼の俳句に興味を持ち、そんな中で種田山頭火に出会った。
「生死(しょうじ)の中の雪降りしきる」という山頭火の句を彫っていた時、仲のよかった和尚の薦めで永平寺本山が募集したポスター原画に応募。これが特選に選ばれた。それまでは、なかなか芽が出なかったのだが。
その後、知らない間に私の作品が、大英博物館に所蔵・展示されていると聞かされた。フクロウをモチーフにした作品を米国の美術館に出したら、評判になったり。忘れたころにボストンの大きな画廊から突然の注文の依頼がきて、縁の下から版木を引っ張り出したこともある。
戦争の善し悪しは論じないが、私は館山で6か月間訓練を受け、そこで死の恐怖と生の喜び、人に対する思いやりを徹底的に教わった。縁がある館山で今後、私が文化面で出来ることがあれば手助けしたい。
(本稿は1月23日に南総文化ホールで行われたトークショーの内容を要約・再編成したものです)
(房日新聞2010.1.26付)

■美術界の有志ら、NPO設立
故・平山郁夫氏 発起人に名連ね
.
明治期の洋画家・青木繁が若き日に滞在し、代表作「海の幸」を制作した館山市布良の小谷家住宅=昨年11月に市有形文化財に指定=の復元・保存を支援しようと、日本美術界の有志らが「青木繁『海の幸』会」を設立。特定非営利活動法人(NPO法人)としてこのほど、法人登記申請が受理された。
[ .. 全文表示へ ]